倒産件数は646件、3カ月ぶりの前年同月比減少
負債総額は1349億8300万円、2カ月連続の前年同月比減少
倒産件数 | 646件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲4.2% |
前年同月 | 674件 |
前月比 | ▲16.6% |
前月 | 775件 |
負債総額 | 1349億8300万円 |
|---|---|
前年同月比 | ▲76.8% |
前年同月 | 5828億4200万円 |
前月比 | +32.4% |
前月 | 1019億2000万円 |
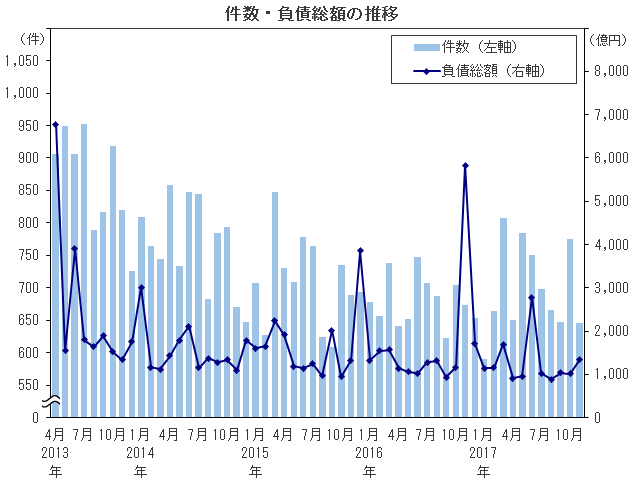
主要ポイント
- ■倒産件数は646件で、前月比は16.6%減、前年同月比も4.2%の減少となり、3カ月ぶりに前年同月を下回った。負債総額は1349億8300万円と、前月比は32.4%増加したものの、前年同月比では76.8%減少し、2カ月連続の前年同月比減少となった
- ■業種別に見ると、7業種中5業種で前年同月を下回った。このうち、運輸・通信業(18件)は前年同月比45.5%の大幅減少となり、2カ月連続の2ケタ減。また、製造業(68件、前年同月比9.3%減)は2カ月連続で前年同月を下回り、2000年以降最少となった。一方、建設業(141件、同14.6%増)、不動産業(18件、同5.9%増)の2業種は前年同月を上回った
- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は542件(前年同月比0.2%増)となり、3カ月連続で前年同月を上回った。構成比は83.9%(同3.6ポイント増)を占めた
- ■負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は407件で前年同月を2.6%下回ったが、構成比では2017年8月(65.9%)に次いで2000年以降2番目に高い63.0%を占めた。資本金規模別では、資本金1000万円未満(個人経営含む)の倒産が419件、構成比は64.9%
- ■地域別に見ると、9地域中4地域で前年同月を下回った。なかでも、東北、関東、九州の3地域は、前年同月比2ケタの減少となった。一方、中国は前年同月比52.4%の大幅増加。中部も2ケタ増となるなど、3地域で前年同月を上回った
- ■負債トップは、ネットカード(株)(旧:オリエント信販(株)、東京都、破産)の594億8900万円
調査結果
■件数・負債総額
ポイント倒産件数は646件、3カ月ぶりの前年同月比減少
倒産件数は646件で、前月比は16.6%減、前年同月比も4.2%の減少となり、3カ月ぶりに前年同月を下回った。負債総額は1349億8300万円と、前月比は32.4%増加したものの、前年同月比では76.8%減少し、2カ月連続の前年同月比減少となった。
要因・背景
件数…業種別では7業種中5業種で、地域別では東北や関東など4地域で前年同月比減少
負債総額…負債100億円以上の倒産は1件にとどまるなど、大型倒産は低水準が続く
■業種別
ポイント5業種で前年同月比減、製造業は2000年以降最少
業種別に見ると、7業種中5業種で前年同月を下回った。このうち、運輸・通信業(18件)は前年同月比45.5%の大幅減少となり、2カ月連続の2ケタ減。また、製造業(68件、前年同月比9.3%減)は2カ月連続で前年同月を下回り、2000年以降最少となった。一方、建設業(141件、同14.6%増)、不動産業(18件、同5.9%増)の2業種は前年同月を上回った。
要因・背景
- 1. 製造業は、堅調な生産、出荷、輸出などを受け、繊維工業(8件、前年同月比27.3%減)、電気機械器具製造(3件、同50.0%減)などが前年同月を下回った
- 2. 建設業は、とび、塗装、内装工事などの職別工事(65件、前年同月比41.3%増)が3カ月連続で前年同月を上回った
■主因別
ポイント「不況型倒産」は542件、構成比は83.9%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は542件(前年同月比0.2%増)となり、3カ月連続で前年同月を上回った。構成比は83.9%(同3.6ポイント増)を占めた。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
要因・背景
- 1. 不況型倒産のうち、建設業、卸売業、小売業の3業種は前年同月比増加
- 2. 「人手不足倒産」は7件、2017年1~11月合計は90件(前年同期比38.5%増)
- 3. 「返済猶予後倒産」は45件(前年同月比40.6%増)、2カ月ぶりの前年同月比増加
- 4. 「チャイナリスク関連倒産」は7件(前年同月比40.0%増)、4カ月ぶりの前年同月比増加
■規模別
ポイント負債5000万円未満の構成比63.0%
負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は407件で前年同月を2.6%下回ったが、構成比では2017年8月(65.9%)に次いで2000年以降2番目に高い63.0%を占めた。資本金規模別では、資本金1000万円未満(個人経営含む)の倒産が419件で構成比64.9%を占めた。
要因・背景
- 1. 負債5000万円未満の倒産では、建設業(80件、前年同月比3.6%減)、卸売業(48件、同17.2%減)、運輸・通信業(10件、同50.0%減)の3業種で前年同月を下回った
- 2. 負債100億円以上の倒産は1件にとどまるなど、大型倒産は低水準が続く
■地域別
ポイント9地域中4地域で前年同月比減少
地域別に見ると、9地域中4地域で前年同月を下回った。なかでも、東北(21件、前年同月比12.5%減)、関東(239件、同13.4%減)、九州(37件、同19.6%減)の3地域は、前年同月比2ケタの減少となった。一方、中国(32件)は前年同月比52.4%の大幅増加、中部(103件、同19.8%増)も2ケタ増となるなど、3地域で前年同月を上回った。
要因・背景
- 1. 東北は、繊維工業、機械器具などの製造業(2件、前年同月7件)が3カ月連続の前年同月比2ケタ減
- 2. 中部は、建設業(29件、前年同月18件)、小売業(23件、同20件)など4業種で前年同月を上回り、全体では3カ月連続の前年同月比増加
■上場企業倒産
上場企業の倒産は発生しなかった。
2017年では、東証1部上場のタカタ(株)(民事再生法、6月)の1件が発生。
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは50.0、調査開始以降2番目の高水準
2017年11月の景気DIは前月比0.9ポイント増の50.0となり、6カ月連続で改善した。
中国への輸出額が10月単月で過去最大を記録するなど、引き続き輸出が拡大基調で推移するなか、「化学品製造」「鉄鋼・非鉄・鉱業」の2業種が3カ月続けて過去最高を更新し、「製造」全体も2カ月連続で過去最高となった。季節需要が追い風となった「運輸・倉庫」など10業界中5業界が、また地域別でも10地域中5地域が50以上になった。景気DIは、消費税率引き上げ前の駆け込み需要が起きた2014年3月(51.0)に次ぎ、2002年の調査開始以降2番目に高い水準となった(なお2014年1月も50.0)。国内景気は、輸出が拡大するなか製造業が2カ月連続で過去最高を更新し、回復が続いた。
輸出の好調継続などを受け、企業主導による回復傾向が続く見込み
世界経済が回復するなか、好調な輸出が今後も国内景気をけん引し、さらにTPP11の大筋合意もプラスに働いていくとみられる。企業業績の改善を背景とした省力化投資の高まりや、開催まで1,000日を切った東京五輪の関連需要を受け、設備投資は増加基調が続き、企業部門が日本経済をけん引していくことが予想される。一方の家計部門は、冬のボーナスの支給総額増加などが個人消費を当面下支えするなど、緩やかに持ち直すと予測される。ただし、人手不足の深刻化が及ぼす悪影響や、地政学的リスクによる為替や株式相場の変動には、注視していく必要がある。
今後の国内景気は、輸出の好調継続などを受け、企業部門が主導するかたちで回復傾向が続くことが見込まれる。
今後の見通し
■生産性向上への取り組み、設備の老朽化が課題に
人手不足が深刻化するなか、生産性向上に向けた動きが活発化してきた。とりわけ省力化・自動化投資に対する需要が高まっている。しかし、減価償却費や有形固定資産など財務データを用いた帝国データバンクの試算によると、中小企業を含め企業設備のビンテージ(設備年齢)は上昇が続いており、生産効率全体を押し下げる要因ともなっている。
そのため、企業の生産性向上には、老朽化した設備に代わり新たな設備の導入が重要となる。法人税減税の議論が行われるなかで、特に設備投資に対する減税措置は、新規投資を促し、生産性向上をもたらすことで、企業の競争力向上につながることが期待される。全国の企業における平均借入金利が9年連続で低下しているものの(帝国データバンク「全国・平均借入金利動向調査」)、資金力の不足しやすい中小企業が行う設備投資を後押しするさらなる政策支援が求められる。
■相次ぐベンチャー企業の倒産、必要とされる経営力向上支援
11月は、情報通信機器端末の製造を手がけるneix(負債26億3200万円、北海道、民事再生)や風力発電機・蓄電池などを製造・販売するWINPRO(負債8億9200万円、新潟県、民事再生)など、ベンチャー企業における経営の行き詰まりが相次いだ。背景として、事業拡大に伴う過大な有利子負債による資金繰り悪化や過年度決算の大幅な見直しが発生するなど、見通しの甘さやずさんな会計処理などが指摘されている。
2017年11月までに、業歴10年未満の企業倒産は1870件発生しており、すでに2016年(1860件)を上回っている。政府は「未来投資戦略2017」において、イノベーションを促すベンチャー企業の創出に対する環境整備を掲げており、ベンチャー企業に対する経営力の向上を支援する必要性が高まっているといえよう。こうしたなかで、ベンチャー企業への資金の供給体制の構築とともに、事業性評価による融資が求められている政府系金融機関や地域金融機関の役割が一段と重要になる。
■2017年の倒産件数は低水準が続くものの、8年ぶりの増加に転じる見込み
国内景気は、好調な輸出を受け製造業を中心として回復が続いている。今後においても、企業業績の改善を背景とした省力化・自動化など設備投資の拡大や東京五輪関連需要など、企業部門がけん引役となり緩やかに上向いていくとみられる。さらに、経済の好循環を本格化させるためには、小売や個人向けサービスなど一進一退の続く個人消費の動向がカギを握ることになろう。
ただし、企業の約5割で人手が足りていないと感じるなど、深刻化する人手不足は今後の企業活動を制約する大きな要因となることが懸念される。また、技術や経営ノウハウの次世代への継承にとって重要となる後継者がいない企業が3社に2社にのぼることが判明し、国内経済や企業経営への影響も危惧される(同「2017年後継者問題に関する企業の実態調査」)。他方、海外では、中東や東アジアなどにおける地政学的リスクの高まりを注視していく必要がある。
こうした状況下において、倒産件数は1~11月累計で7680件となり、前年同期を2.3%上回っている。そのため、2017年の年間倒産件数は低水準が続くものの、2009年以来8年ぶりの増加に転じると見込まれる。

