倒産件数は731件、4カ月連続の前年同月比減少
負債総額は933億200万円、2カ月連続の前年同月比減少
倒産件数 | 731件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲6.8% |
前年同月 | 784件 |
前月比 | +18.3% |
前月 | 618件 |
負債総額 | 933億200万円 |
|---|---|
前年同月比 | ▲3.0% |
前年同月 | 961億7200万円 |
前月比 | +12.7% |
前月 | 827億7000万円 |
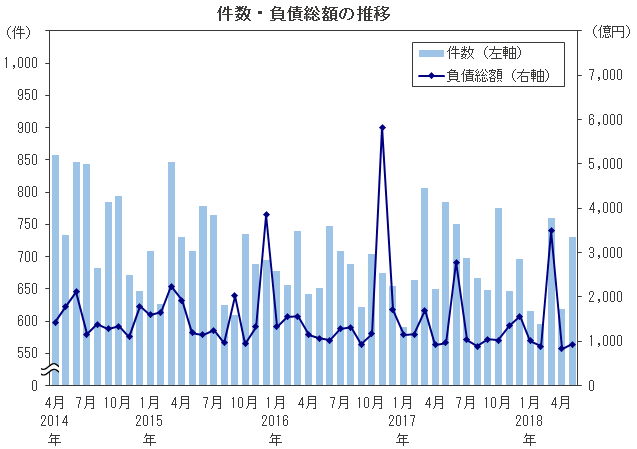
主要ポイント
- ■倒産件数は731件(前年同月比6.8%減)と、4カ月連続で前年同月を下回った。負債総額は933億200万円(同3.0%減)と、2カ月連続で前年同月を下回った
- ■業種別に見ると、7業種中4業種で前年同月を下回った。なかでも、建設業(120件、前年同月比18.4%減)、製造業(80件、同29.8%減)、不動産業(24件、同20.0%減)の3業種は前年同月比2ケタ減となった。一方、卸売業(102件、同5.2%増)、サービス業(183件、同8.3%増)など3業種は前年同月を上回った
- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は587件(前年同月比7.8%減)となり、4カ月連続で前年同月を下回った。構成比は80.3%(同1.0ポイント減)を占めた
- ■負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は462件(前年同月比1.1%減)となった。構成比は63.2%を占め、小規模倒産が大半を占める傾向が続いた。資本金規模別では、資本金1000万円未満(個人経営含む)の倒産が479件で構成比65.5%を占めた
- ■地域別に見ると、9地域中6地域で前年同月を下回った。このうち、北海道(23件、前年同月比17.9%減)は6カ月連続、関東(267件、同12.2%減)は4カ月連続の前年同月比減少となった。一方、中国(30件、同66.7%増)など3地域は前年同月を上回った
- ■負債トップは、(株)ビバック(東京都、破産)の185億9086万円
調査結果
■件数・負債総額
ポイント倒産件数は731件、4カ月連続の前年同月比減少
倒産件数は731件(前年同月比6.8%減)と、4カ月連続で前年同月を下回った。負債総額は933億200万円(同3.0%減)と、2カ月連続で前年同月を下回った。
要因・背景
件数…業種別では建設業など4業種で、地域別では北海道など6地域で前年同月比減少
負債総額…負債100億円以上の倒産が1件発生も、小規模倒産が大半を占めた
■業種別
ポイント建設業、製造業など4業種で前年同月比減少
業種別に見ると、7業種中4業種で前年同月を下回った。なかでも、建設業(120件、前年同月比18.4%減)、製造業(80件、同29.8%減)、不動産業(24件、同20.0%減)の3業種は前年同月比2ケタ減となった。一方、卸売業(102件、同5.2%増)、サービス業(183件、同8.3%増)など3業種は前年同月を上回った。
要因・背景
- 1. 建設業は、都市部でのオフィスビルやホテルの建設増加を受け、設備工事(16件、前年同月比56.8%減)が2000年以降最少となるなど、幅広く減少
- 2. 製造業は、機械関連の堅調な推移を背景に、鉄鋼、非鉄金属・金属製品製造(5件、前年同月比73.7%減)、電気機械器具製造(3件、同70.0%減)などの減少が目立った
■主因別
ポイント「不況型倒産」の構成比80.3%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は587件(前年同月比7.8%減)となり、4カ月連続で前年同月を下回った。構成比は80.3%(同1.0ポイント減)を占めた。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
要因・背景
- 1.不況型倒産を業種別に見ると、小売業(149件)が構成比25.4%を占め最多
- 2.「人手不足倒産」は11件(前年同月比37.5%増)、2カ月連続の前年同月比増加
- 3.「後継者難倒産」は28件(前年同月比3.7%増)、4カ月ぶりの前年同月比増加
- 4.「返済猶予後倒産」は41件(前年同月比19.6%減)、4カ月連続の前年同月比減少
■規模別
ポイント負債5000万円未満の構成比63.2%
負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は462件(前年同月比1.1%減)となった。構成比は63.2%を占め、小規模倒産が大半を占める傾向が続いた。資本金規模別では、資本金1000万円未満(個人経営含む)の倒産が479件で構成比65.5%を占めた。
要因・背景
- 1. 負債5000万円未満の倒産では、サービス業(129件)が構成比27.9%(前年同月比2.9ポイント増)を占め最多。小売業(121件)が同26.2%(同2.9ポイント減)で続く
- 2. 負債100億円以上の倒産は、(株)ビバック(負債185億9086万円、東京都)の1件発生のみ
■地域別
ポイント北海道、関東など6地域で前年同月比減少
地域別に見ると、9地域中6地域で前年同月を下回った。このうち、北海道(23件、前年同月比17.9%減)は6カ月連続、関東(267件、同12.2%減)は4カ月連続の前年同月比減少となった。一方、中国(30件、同66.7%増)など3地域は前年同月を上回った。
要因・背景
- 1.北海道は卸売業(5件)など4業種で増加も、建設業(1件、前年同月比85.7%減)、サービス業(4件、同50.0%減)の2業種で大幅減となり、地域全体を押し下げた
- 2.関東は、建設業が7都県すべてで前年同月比減少。なかでも、東京五輪関連需要などを背景に、東京都の建設業は4カ月連続の2ケタ減
■上場企業倒産
上場企業の倒産は発生しなかった。
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは49.4、国内景気は2カ月連続で悪化
2018年5月の景気DIは前月比0.4ポイント減の49.4となり、2カ月連続で悪化した。
5月の国内景気は、原油価格が1バレル=72ドル台(WTI)とおよそ3年半ぶりの高値をつけガソリンや軽油などの価格が上昇したことから企業や個人のコスト負担が増し、景況感を押し下げる要因となった。加えて、食品や電気料金の値上げで消費マインドが弱含んだことや人手不足の深刻化を受け、小売業およびサービス業の消費関連業種が悪化。米トランプ政権による保護貿易主義の拡大も企業マインドにマイナスに響き、1年11カ月ぶりに2カ月続けて悪化した。日本経済を取り巻く環境に不透明感が増すなか、国内景気は原油価格上昇が企業や個人のコスト負担増を招いたことが響き、足踏み状態が続いた。
国内景気は輸出や設備投資がけん引も、海外リスクの顕在化には注視が必要
国内景気は、世界経済の回復を背景に輸出の増加が続くほか、設備投資も省力化や東京五輪向けの需要を受けて堅調に推移すると見込まれる。個人消費は夏季賞与などを含めた賃金上昇や消費税率引き上げにともなう駆け込み需要から、緩やかな回復が続くであろう。一方で、米中の貿易摩擦激化や欧州における景気減速懸念、中東などの地政学的リスクの高まりといった海外情勢の動向については、注意深く見守る必要がある。また人手不足などにともなうコスト負担の増加や経済政策の停滞もマイナスの影響を及ぼすであろう。今後の国内景気は輸出や設備投資がけん引していくと見込まれるものの、海外リスクの顕在化が景気を下押しする可能性について注視する必要がある。
今後の見通し
■老舗企業倒産が11件発生、ニーズを捉えた変革が一段と重要に
老舗倒産の存在感が徐々に高まっている。業歴100年以上の老舗倒産は5月に11件発生。とりわけ、業歴184年の老舗和菓子メーカーである花園万頭(負債22億円、東京都、破産)や明治10年創業の納豆製造業者の森口加工食品(負債5億600万円、京都府、特別清算)、大正元年創業の酒小売店のトミナガ(負債3億7800万円、京都府、破産)など、飲食料品関連が約半数にのぼった。大手量販店との競争激化や消費者ニーズの変化に伴う販売不振に加えて、原材料費や人件費が高騰するなか、過度な設備投資で資金繰りに窮するケースが散見された。
2017年度における老舗企業の倒産・休廃業・解散件数は461件と、2000年度以降で最多を更新した(帝国データバンク「老舗企業倒産・休廃業・解散の動向調査」2018年5月)。老舗企業の倒産では後継者難問題に加えて、規制や産業構造など事業環境の激しい変化に対応できず、市場から退出する事例が多くみられる。伝統とともに、ニーズを的確にとらえた変革が一段と重要となっている。
■改正銀行法が施行、銀行とフィンテック企業の連携でビジネスモデルの転換も
2018年6月1日、電子決済代行業者の定義のほか、銀行のオープン・イノベーション(連携・協働による革新)に対する取り組みなどを規定した改正銀行法が施行されたことを受け、全国銀行協会は銀行とフィンテック企業のAPI利用契約の条文例を公表した。改正法では、電子決済代行業は内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ営むことができないとし、銀行との契約締結が義務化された。一方、銀行にはオープンAPI(銀行と外部の事業者との間の安全なデータ連携を可能にする接続仕様・仕組み)の体制を整備することを努力義務とした。
フィンテックの動きが世界的に加速していることを背景に、利用者保護の観点から、制度的な枠組みの整備が必要とされている。そのため、今回の体制整備とルール策定により、オープン・イノベーションを進める銀行、さらに銀行が提供するオープンAPIに対応するフィンテック企業が、今後の業界をリードしていくとみられている。 金融情報が急速にネットワーク化されるなか、金融機関の店舗を中心としたビジネスモデルは大きく変わる可能性がある。それは同時に、企業と銀行のかかわり方にも影響するとみられ、中小企業経営にどのような影響を与えるかが注目されよう。
■倒産動向は抑制された状態で推移
国内景気は、世界経済の回復を通じて輸出が増加すると見込まれるほか、省力化需要や東京五輪需要などを受けて設備投資も堅調に推移するとみられる。また、夏季賞与や賃金の上昇は個人消費を下支えすると予測される。さらに、政策面では、2018年度税制改正により、中小企業・小規模企業の事業承継に向けた支援策が強化されているほか、事業譲渡に対する税負担の軽減措置が新設されたことは、円滑な事業承継に向けて好材料となろう。 他方、深刻化する人手不足のほか、貿易摩擦の激化や欧州の景気減速懸念、中東の地政学的リスクなど、海外リスクの顕在化が景気下押しに対する懸念材料といえる。また、4月のスマートデイズ(東京都、民事再生→破産)に続き、シェアハウス運営業者のゴールデンゲイン(東京都、破産)が経営破たんするなど、低金利下で生じた個人による投資リスクの影響は、今後も注視していく必要がある。
こうした状況の下、5月の倒産件数は731件(前年同月比6.8%減)となり、2018年は累計3320件(前年同期比5.0%減)となっている。ビジネス環境が大きく変わる可能性が高まっているなかで、当面の倒産動向は抑制された状態で推移すると見込まれる。

