倒産件数は694件、2013年7月以来2年5カ月ぶり2カ月連続の前年同月比増加
負債総額は3855億9300万円、2015年最大を記録
倒産件数 | 694件 |
|---|---|
前年同月比 | +7.3% |
前年同月 | 647件 |
前月比 | +0.7% |
前月 | 689件 |
負債総額 | 3855億9300万円 |
|---|---|
前年同月比 | +115.1% |
前年同月 | 1792億4600万円 |
前月比 | +190.2% |
前月 | 1328億7000万円 |
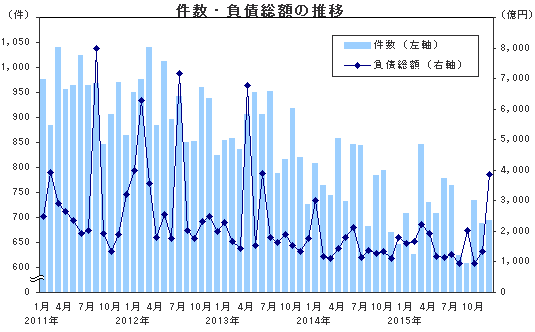
主要ポイント
- ■倒産件数は694件で、前月比で0.7%増加、前年同月比でも7.3%増加となった。前年同月比が2カ月連続で増加したのは、2013年7月以来2年5カ月ぶり
- ■負債総額は3855億9300万円で、前月比190.2%の増加、前年同月比115.1%の増加と、ともに3ケタの増加幅となった
- ■業種別に見ると、7業種中5業種で前年同月を上回り、不動産業(30件、前年同月比30.4%増)、卸売業(120件、同29.0%増)は前年同月比2ケタの大幅増加。一方、運輸・通信業(18件、同30.8%減)と建設業(129件、同5.1%減)は前年同月を下回った
- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の構成比は80.3%(前月85.6%、前年同月80.7%)。2014年12月(522件、構成比80.7%)以降13カ月連続で80%台となった
- ■「チャイナリスク関連倒産」は5件(前年同月比16.7%減)判明
- ■「円安関連倒産」は17件(前年同月比61.4%減)判明、4カ月連続で前年同月比減少
- ■「返済猶予後倒産」は40件(前年同月比66.7%増)判明、2カ月連続で前年同月比増加
- ■負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は398件(前年同月比8.7%増)。また、単月で負債1000億円以上の倒産が2件発生したのは、2012年7月以来3年5カ月ぶり
- ■地域別に見ると、四国(16件、前年同月比45.5%増)など9地域中5地域で前年同月比2ケタの大幅増。一方減少した地域はいずれも前年同月比1ケタの減少率にとどまる。
- ■負債トップは、ラムスコーポレーション(株)(東京都、会社更生法)の1400億円
調査結果
■件数・負債総額
ポイント2013年7月以来2年5カ月ぶりの2カ月連続前年同月比増加
倒産件数は694件で、前月比で0.7%増加、前年同月比でも7.3%増加となった。前年同月比が2カ月連続で増加したのは、2013年7月以来2年5カ月ぶり。負債総額は3855億9300万円で、前月比190.2%の増加、前年同月比115.1%の増加となり、2015年最大となった。
要因・背景
件数…業種では不動産業、卸売業の2業種で、地域では倒産件数全体の約4割を占める関東のほか、東北、北陸、中国、四国の5地域で、増加率が前年同月比2ケタの大幅増加
負債総額…負債1000億円以上の倒産が2件発生し、負債総額を押し上げた
■業種別
ポイント7業種中5業種で前年同月比増加
業種別に見ると、7業種中5業種で前年同月を上回り、なかでも不動産業(30件、前年同月比30.4%増)、卸売業(120件、同29.0%増)の2業種は前年同月比2ケタの大幅増加となった。一方、運輸・通信業(18件、同30.8%減)と建設業(129件、同5.1%減)の2業種は前年同月を下回り、なかでも運輸・通信業は前年同月比2ケタの大幅減少となった。
要因・背景
- 1. 卸売業…木材や建設用石材などを含む木材・建築材料卸売業(15件、前年同月比200.0%増)や、生鮮品中心に飲食料品卸売業(21件、同31.3%増)などが大幅増加
- 2.運輸・通信業…軽油など燃料価格が下落したことも影響し、一般貨物自動車運送業(8件、前年同月比50.0%減)で大幅に減少した
■主因別
ポイント「不況型倒産」の構成比80.3%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は557件(前年同月比6.7%増)となった。構成比は80.3%となり、前月(85.6%)、前年同月(80.7%)をともに下回ったものの、2014年12月(522件、構成比80.7%)以降13カ月連続で80%台となった。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、 業界不振を「不況型倒産」として集計
要因・背景
- 1.「チャイナリスク関連倒産」は5件(前年同月比16.7%減)判明
- 2.「円安関連倒産」は17件(前年同月比61.4%減)判明、4カ月連続で前年同月比減少
- 3.「返済猶予後倒産」は40件(前年同月比66.7%増)判明、2カ月連続で前年同月比増加
■規模別
ポイント負債5000万円未満の構成比57.3%
負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は398件(前年同月366件)で、前年同月を8.7%上回り、構成比は57.3%と38カ月連続で過半数を占めた。一方、負債50億円以上の倒産は3件(前月5件、前年同月4件)発生した。また、単月で負債1000億円以上の倒産が2件発生したのは、2012年7月以来3年5カ月ぶり。
要因・背景
- 1. 負債5000万円未満の倒産、サービス業で大幅増加も、運輸・通信業や建設業で減少
- 2. 負債50億円以上の倒産、2012年1月(8件)以降48カ月連続で10件未満にとどまった
■地域別
ポイント9地域中5地域で前年同月比増加
地域別に見ると、北陸(19件、前年同月比72.7%増)、四国(16件、同45.5%増)、東北(26件、同36.8%増)など、9地域中5地域で、前年同月比2ケタの大幅増加となった。一方、九州(51件、同7.3%減)、中部(81件、同5.8%減)など4地域は前年同月を下回ったが、いずれも前年同月比1ケタの減少率にとどまった。
要因・背景
- 1. 関東は、不動産業(14件、前年同月比75.0%増)など4業種で前年同月比2ケタの大幅増
- 2. 中国は、サービス業が増加し、2015年5月以来7カ月ぶりに前年同月比が増加
■主な倒産企業
負債トップは、ラムスコーポレーション(株)(東京都、会社更生法)の1400億円。以下、(株)MARU(旧:AIJ投資顧問(株)、東京都、破産)の1313億円、市川総業(株)(東京都、民事再生法)の92億5900万円がこれに続く。
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは44.7、国内景気の停滞感続く
2015年12月の景気DIは前月比0.1ポイント減の44.7となり3カ月ぶりに悪化した。
2015年の景気DIは年初と比較して0.8ポイント増と改善したものの、4月以降、悪化または横ばいが7カ月あり、景気は停滞感の漂う一年となった。 12月は、エルニーニョ現象が生鮮市場に悪影響をもたらしたうえ、冬物衣料の販売不振が服飾品小売の景況感を大幅に悪化させる背景ともなった。また、石油業界では、原油価格が再び下落に転じたものの販売価格の低下は大きく、収益を圧迫する要因となった。他方、公共工事の減少が続くなか、くい打ちデータ改ざんが建設や不動産などの業界に悪影響を徐々に及ぼしてきている。さらに、中国経済の減速を受けて、中国向け製品の減産に踏み切る動きも表れた。国内景気は、公共工事減少や暖冬による季節商材の販売不振などで地方の景気低迷が長引いており、停滞が続いている。
今後の国内景気は下振れリスクをはらみつつ推移する見通し
2016年1月は、日経平均株価が米国や上海株式市場の影響を受けた大幅下落で幕を開けた。中国経済の減速が引き続き懸念されるほか、中東における政情不安の高まりは、原油輸入の8割を中東に依存する日本経済の大きな懸念材料となる。他方、米国が原油輸出を解禁したことで、原油価格の低水準は継続するとみられ、企業のコスト負担を和らげる要因となる。また、米国金利引き上げや円高など海外の経済動向に関する悪材料が重なる。アベノミクス第二弾の実行、企業業績の改善による賃金上昇や設備投資は好材料となるが、今後の景気は、中東有事次第では原油価格高騰によりインフレ懸念が生じることで消費減退などに影響を及ぼす可能性もあり、下振れリスクをはらみつつ推移するとみられる。
今後の見通し
■倒産件数は8517件、2年連続で1万件を下回り2000年以降3番目の低水準
2015年の企業倒産件数は8517件と、2年連続で1万件を下回り、全業種および全地域で前年比減となった。業種別では、建設業(前年比13.3%減)、運輸・通信業(同16.5%減)、不動産業(同15.4%減)が減少率2ケタ台となり、特に民需を中心に建設投資拡大の追い風を受けた建設業は7年連続で前年比減少、構成比も18.9%と、2006年の27.9%と比べ9.0ポイント減少し減少傾向が顕著となった。構成比を見れば、小売業が21.2%(2006年:17.2%)、サービス業は20.6%(同:16.7%)と、2年連続で全体の2割を超え、消費の回復が遅れていることが倒産動向にも表れつつある。 態様別では民事再生法による倒産が246件(前年比15.5%減)と、前年(291件)を下回り、同法施行(2000年4月)以降、年間件数最少を更新した。2013年以降、3年連続して減少率2ケタ台と大きく減少している背景には、再建型手続きが困難な中小零細企業の倒産が増加していることに加え、事業再生ADRや中小企業再生支援協議会の活用、各種ファンドの活用、特別清算を活用した第二会社方式による事業継続など、事業再生の選択肢が多様化している点がある。
■不透明な運用や偽装など、不祥事が企業や事業の存否を問う時代に
「企業統治元年」と言われた2015年は、6月に上場企業に対して「企業統治指針」の適用が開始され、企業のガバナンスやコンプライアンスへの注目度がより高まった。そうしたなか相次いで発覚したのが企業による不祥事だ。診療報酬債権を運用していたオプティファクター(11月、破産)や、企業年金の運用を受託していたMARU(旧:AIJ投資顧問、12月、破産)など、不透明な資産運用を巡り証券取引等監視委員会の調査や摘発を受けた企業の大型倒産も続いた。不祥事やトラブルで企業や事業の存否が問われるのは大企業に限ったことではなく、肥料の成分表示偽装を長年続けていた太平物産(11月、民事再生法)や、学校給食での異物混入で自治体から契約を解除された徳島屋(12月、民事再生法)などが倒産した。不祥事やトラブルは取引先や消費者離れに直結し、企業規模を問わず市場からの退出を余儀なくされる時代であることが鮮明となっている。
■人手不足や資金調達難での倒産も、「海外情勢」など国内外の複合リスク懸念
近年の倒産の低位推移は、2013年3月の金融円滑化法の期限到来後も金融機関が高水準で中小企業の弁済リスケに応じているという政策面での抑制力が大きい。2016年の景気のベストシナリオとして期待されるのは、自動車や化学、ゼネコンなど大手企業の好業績に支えられ、雇用・所得環境の改善が続き、流通、サービスなど国内需要の本格回復につながり、消費増税を前に住宅や自動車など高額商品の駆け込み需要の開始も景気押し上げ要因となることだ。ただし、雇用環境の改善にともない建設業や飲食業、サービス業、運送業など幅広く人手不足感が高まることが予想されるほか、弁済リスケを受けている企業の中にはすでに過大な金融債務を抱えている企業も多く、新規融資が受けられず資金調達ができなかった場合は倒産を余儀なくされるケースも発生しよう。
一方、各種リスクも山積している。その筆頭が不安定な海外情勢だ。欧州でのテロの脅威や難民問題に加え、年明けから中東情勢の変動や北朝鮮の核実験など地政学リスクが高まっているなか、日米株安に加え上海株式市場では株価急落でサーキットブレーカーが連続して発動されるなど波乱の幕開けとなった。海外情勢の不安定さは原油価格や株式・為替動向の変動に直結する。原油安による燃料価格の下落はプラスとなる業界がある一方で、国内市場縮小で安値販売競争に陥っているガソリンスタンド経営業者への影響は必至だ。また、円安基調が定着しつつあるなかでの想定外の急激な為替変動は、繊維や食品など輸入商材への依存度が高い業界を直撃する。
国内では、今冬の暖冬による小売業やサービス業への影響など、気候や災害による自然リスク懸念のほか、昨年発生したくい打ちデータ改ざん問題の影響を受け地方の一部では建設工事の先延ばしが発生するなど、同問題が建設業界に及ぼす影響が顕在化しつつある。2016年夏の参院選や2017年に予定される消費税率10%への引き上げを前に、現政権では法人税減税や設備投資への優遇措置を取り入れており、ゾンビ企業の処理を加速させる様な金融政策の見直しを行うことは考えづらい。ただし、2016年は国内外における各種のリスクが複合的に影響し、倒産が増加傾向に転じる可能性は否定できず、予断を許さない状況が続く。

