倒産件数は625件、5カ月連続の前年同月比減少
負債総額は964億8500万円、2000年以降最小を記録
倒産件数 | 625件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲8.5% |
前年同月 | 683件 |
前月比 | ▲18.3% |
前月 | 765件 |
負債総額 | 964億8500万円 |
|---|---|
前年同月比 | ▲29.9% |
前年同月 | 1376億7400万円 |
前月比 | ▲22.3% |
前月 | 1241億5700万円 |
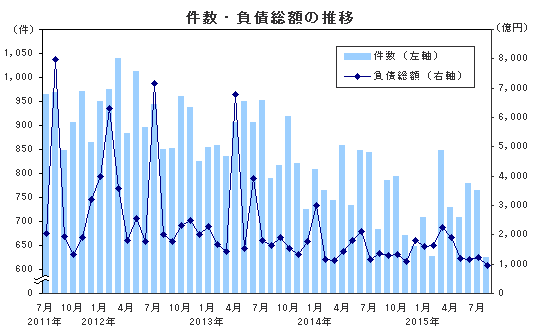
主要ポイント
- ■倒産件数は625件で、前年同月比8.5%減少し、5カ月連続で前年同月を下回った。一方で、同減少率は4カ月連続で1ケタ台にとどまっている
- ■負債総額は964億8500万円となり、前年同月比29.9%の減少で、2000年以降初めて1000億円を割り込み、最小記録となった
- ■業種別に見ると、7業種中5業種が前年同月を下回り、とりわけ不動産業(15件、前年同月比42.3%減)と運輸・通信業(21件、同41.7%減)は前年同月比で40%以上減少した
- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は540件(前年同月比3.1%減)となった
- ■負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は350件(前年同月比4.6%減)で、構成比は56.0%と、前年同月を2.3ポイント上回った。一方、負債10億円以上の倒産は15件(同25.0%減)となり、8月としては2000年以降最少となった
- ■地域別に見ると、9地域中7地域で前年同月を下回った。なかでも、北陸(12件、前年同月24件)は前年同月比50.0%の大幅減少となったのに対し、近畿(174件、同151件)は同15.2%の増加、四国(7件、同7件)では前年同月比で横ばいとなった
- ■上場企業の倒産は発生しなかった
- ■負債トップは、名阪ワシントンクラブ(株)(三重県、破産)の144億円。以下、(株)不二屋ビルデング(東京都、民事再生法)の61億5300万円、(株)名阪フレンドリーパーク(三重県、破産)の36億円がこれに続く
調査結果
■件数・負債総額
ポイント件数は5カ月連続の前年同月比減少、負債総額は2000年以降最小を記録
倒産件数は625件で、前年同月比8.5%減少し、5カ月連続で前年同月を下回った。一方で、同減少率は4カ月連続で1ケタ台にとどまっている。負債総額は964億8500万円となり、前年同月比29.9%の減少で、2000年以降初めて1000億円を割り込み、最小記録となった。
要因・背景
件数…2000年以降、8月としては2000年の578件に次ぐ2番目の低水準となったほか、リーマン・ショックの発生した2008年9月以降では最少となった
負債総額…負債10億円以上の倒産は15件(前年同月20件)で、大型倒産が抑制されている
■業種別
ポイント7業種中5業種で前年同月比減少
業種別に見ると、7業種中5業種が前年同月を下回った。とりわけ不動産業(15件、前年同月比42.3%減)と運輸・通信業(21件、同41.7%減)は前年同月比で40%以上減少したほか、運輸・通信業と卸売業(87件、同17.1%減)はリーマン・ショック後では最少記録となった。一方、製造業(93件、同24.0%増)と小売業(130件、同4.8%増)は前年同月を上回った。
要因・背景
- 1. 運輸・通信業…燃料価格が下落したことが影響し、一般貨物自動車運送業で大きく減少した
- 2. 製造業…国内自動車販売台数の減少などによる鉄鋼需要が後退していることもあり、鉄鋼業や非鉄金属・金属製品製造業などで増加
■主因別
ポイント「不況型倒産」の構成比86.4%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は540件(前年同月比3.1%減)となった。構成比は86.4%(前月84.4%、前年同月81.6%)と、前月を2.0ポイント、前年同月を4.8ポイントそれぞれ上回った。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、 業界不振を「不況型倒産」として集計
要因・背景
- 1.「返済猶予後倒産」は28件(前年同月比15.2%減)判明
- 2.「円安関連倒産」は24件(前年同月比9.1%増)判明し、前年同月比では20カ月連続での増加となったが、前月比では横ばいとなった
■規模別
ポイント負債5000万円未満の構成比56.0%
負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は350件(前年同月比4.6%減)で、構成比は56.0%と、前年同月を2.3ポイント上回った。一方、負債10億円以上の倒産は15件(同25.0%減)となり、8月としては2000年以降最少となった。資本金別では、個人経営と資本金1000万円未満の合計が350件となり、構成比は56.0%を占めた。
要因・背景
- 1. 個人経営など零細企業の占める割合が増加し、小規模倒産の構成比を押し上げている
- 2. 負債10億円以上の倒産(15件)、2000年以降2015年1月に次ぐ2番目の低水準を記録
■地域別
ポイント9地域中7地域で前年同月比減少
地域別に見ると、9地域中7地域で前年同月を下回った。なかでも、北陸(12件、前年同月24件)は前年同月比50.0%の大幅減少となった。一方、近畿(174件、同151件)は同15.2%の増加、四国(7件、同7件)では前年同月比で横ばいとなった。
要因・背景
- 1. 北陸は2015年3月の新幹線開通による特需が引き続き継続しており、石川県では開業翌月となる4月から5カ月連続の前年同月比減少を記録している
- 2. 近畿は製造業(23件、前年同月比109.1%増)を中心に、幅広い業種で増加
- ■上場企業倒産
上場企業の倒産は発生しなかった。
2015年の上場企業倒産は、スカイマーク(株)(1月、負債710億8800万円)、江守グループホールディングス(株)(4月、同711億円)の2件にとどまっている。■主な倒産企業
負債トップは、名阪ワシントンクラブ(株)(三重県、破産)の144億円。以下、(株)不二屋ビルデング(東京都、民事再生法)の61億5300万円、(株)名阪フレンドリーパーク(三重県、破産)の36億円がこれに続く。
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは45.1%、景況感は二分化されるも悪化は小幅にとどまる
2015年8月の景気DIは前月比0.3ポイント減の45.1となり2カ月ぶりに悪化した。
8月は、公共工事の発注が先送り・縮小されたほか、輸出用工作機械の大幅な受注減少や大手電機メーカーの発注縮小、国内自動車生産の低迷などで生産活動も弱含んだ。また、雇用状況のひっ迫や最低賃金の引き上げにともなう人件費上昇が続くなか、価格転嫁が困難な企業の収益を圧迫している。金融市場では、中国における人民元相場の切り下げや上海株式市場急落を発端として大きく混乱した。他方、有効求人倍率は23年5カ月ぶりの高水準だったほか、お盆期間の天候が安定し旅行需要などが堅調だった。さらに、プレミアム商品券やインバウンド消費の恩恵を受けた『小売』が改善するなど、業種や地域、企業規模において景況感が二分化される傾向が表れてきた。国内景気は、中国発の世界同時株安で下押しされたものの、雇用・所得環境などは安定的に推移しており、景況感の悪化は小幅にとどまった。国内景気はやや弱含みで推移するも、年明け後に上向き傾向強まる
中国経済の成長鈍化などで新興国向け輸出の減速による生産調整の長期化や、企業の投資意欲の低下が懸念される。他方、2016年春の大卒採用活動の解禁で、企業の採用活動が活発化するなか、新規求人倍率や有効求人倍率は記録的な改善を見せており、雇用者所得は上昇していくとみられる。また、政治日程の都合などで手薄となっていた経済政策は、来年の参議院選挙に向けて再び加速すると見込まれる。さらに、米国における金利引き上げの後ずれ見通しはプラス材料といえる。今後の国内景気は、年内はやや弱含みで推移するものの、景気対策の実施などで年明けから上向き傾向が強まると予測される。
今後の見通し
■8月の倒産は低位水準続くが、業種間の倒産動向に構造変化表れる
8月の倒産件数は625件(前年同月比8.5%減)と5カ月連続で前年同月比で減少。負債総額は964億8500万円(同29.9%減)で、2000年以降で最小となり初めて1000億円を下回った。件数の業種別構成比を見ると、建設業21.4%、サービス業21.0%、小売業20.8%の順となっている。従来、構成比25~30%前後でトップとなっていた建設業の構成比が近年低下傾向にあり、2015年以降は20%を割り込み、小売業、サービス業を下回る月も多く発生している(4頁参照)。
建設業は公共工事や民間設備投資の回復により倒産が抑制されており、成熟業界として新業態が市場に参入する可能性が低い業界でもある。対して参入障壁が低く、スマートフォンのような新たなツールが普及し、新サービスの参入が多い小売業、サービス業は企業代謝も活発といえ、産業構造の変化が倒産動向にも表れつつあるといえよう。企業数が全体の3割弱を占める建設業の倒産が減少していることは、全体の倒産が沈静化している一つの要因にもなっている。公共工事の減少は地方を中心に注意深く見守る必要があるが、一方で小売業、サービス業では構造変化に対応できない企業の淘汰が進む可能性もある。
■チャイナリスクへの関心高まる
8月は中国・天津市の倉庫爆発事故や上海市場の株価下落など、中国におけるさまざまなリスクが表面化、爆発事故では日系メーカーなどが工場の一時操業停止を余儀なくされるなど、企業活動に支障をきたす事態となった。中国国内の人件費が上昇するなか生産コストが高騰しているほか、品質管理の難しさや売掛金の回収問題、入居施設をめぐるトラブルなど、中国におけるリスク要因を背景とする倒産は断続的に発生している。これまで高い成長を続けてきた中国経済だが、最近ではGDPの成長率が右肩下がりに推移しており、7%を維持するのがやっとの状態になりつつある。過剰在庫が表面化している鉄鋼業界などでは価格が下落傾向にあり、国内企業もそれに巻き込まれる形となっている。中国におけるバブル経済の崩壊を危惧する声が高まりつつあるなか、倒産リスクとしての中国の動向には引き続きウォッチが必要だろう。
■プラス、マイナス、さまざまな要因が企業業績に影響
国内では、7月の有効求人倍率(1.21倍、季節調整値)が23年5カ月ぶりの高水準となるなど、雇用や所得環境の改善が進んでいる。ただ一方で、飲食店や情報サービスなど、人手不足が深刻化している業界では人材確保のために人件費が高騰して収益を圧迫するケースも見られる。また、原油価格の下落は運輸業界のみならず、エネルギー関連や観光関連など幅広い業種に恩恵をもたらすことが期待されるが、一方で燃料価格の値下がりを受けて、運送費の値下げ要請を受ける動きもあり、一概にプラスに作用するとは言い難い面もある。
また2016年のマイナンバー制度の運用開始を前に、10月から通知カードの配布がスタートする。まずは税金、社会保障、災害関連分野での導入となるが、とりわけ注目されるのが社会保障分野における展開だろう。中小零細企業の倒産事例をみると、税金や社会保険料が滞納されているケースが多く見受けられる。今後、特に資金繰りに窮している零細企業にとっては少なからず影響を受けることになるだろう。
8月下旬にかけて世界的に乱高下した株価は、足元では落ち着きを取り戻しつつある。しかし、一時的とはいえ混乱を来たした金融市場を受けて、企業や消費者の心理的な動揺は投資や消費などの活動に影響を与えることも考えられる。差し当たり企業倒産が増加傾向に大きく転じる可能性はないと思われるが、中小企業のなかでも特に返済猶予を受けている零細企業にとっては倒産や廃業など、市場から退場する選択を迫られるケースが出始めるかもしれない。

