倒産件数は765件、4カ月連続の前年同月比減少
負債総額は1241億5700万円、3カ月ぶりの前年同月比増加
倒産件数 | 765件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲9.4% |
前年同月 | 844件 |
前月比 | ▲1.8% |
前月 | 779件 |
負債総額 | 1241億5700万円 |
|---|---|
前年同月比 | +7.7% |
前年同月 | 1152億3800万円 |
前月比 | +8.3% |
前月 | 1146億9400万円 |
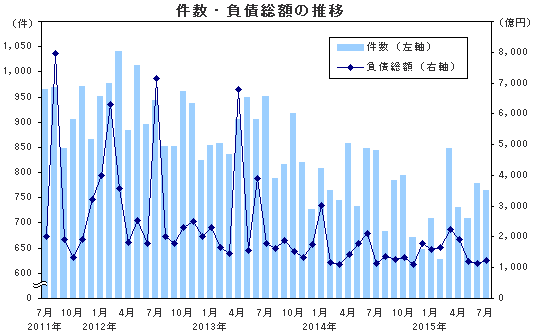
主要ポイント
- ■倒産件数は765件で、前年同月比で9.4%減少し、4カ月連続で前年同月を下回った。同減少率は1ケタ台にとどまっており、倒産件数の下げ止まりの傾向が見られる
- ■負債総額は1241億5700万円、前年同月比7.7%の増加で、3カ月ぶりに前年同月を上回る
- ■業種別に見ると、7業種中5業種が前年同月を下回り、なかでも、小売業(151件、前年同月比17.0%減)をはじめ、建設業(155件、同15.8%減)、卸売業(118件、同10.6%減)の3業種が2ケタの大幅減少となった
- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は646件(構成比84.4%減)となった
- ■「円安関連倒産」は24件(前年同月比9.1%増)判明し、19カ月連続の前年同月比増加
- ■負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は433件(前年同月比8.8%減)で、構成比は56.6%と、前年同月を0.3ポイント上回った。一方、負債10億円以上の倒産は23件(同43.8%増)に上った
- ■地域別に見ると、9地域中6地域で前年同月を下回った。なかでも、北陸(16件、前年同月比42.9%減)、四国(12件、同33.3%減)の2地域は前年同月と比べ3割以上減少した
- ■上場企業の倒産は発生しなかった
- ■負債トップは、(株)goodgo99(東京都、破産)の85億円。以下、(株)ジョー・コーポレーション(愛媛県、破産)の72億7500万円、(株)榎並工務店(大阪府、民事再生法)の49億4400万円、つくば管財(株)(茨城県、特別清算)の44億円がこれに続く
調査結果
■件数・負債総額
ポイント件数は4カ月連続で前年同月を下回るも、負債総額は増加
倒産件数は765件で、前年同月比9.4%の減少となり、4カ月連続で前年同月を下回った。同減少率は3カ月連続で1ケタ台にとどまっている。負債総額は1241億5700万円、前年同月比7.7%の増加で、3カ月ぶりに前年同月比増加となった。
要因・背景
件数…小売業(前年同月比17.0%減)や建設業(同15.8%減)など3業種が前年同月比2ケタの大幅減少となった
負債総額…負債10億円以上の倒産が増加したほか、1社あたりの平均負債額が約1億6200万円(前年同月約1億3700万円)となり、前年同月比18.2%増加している
■業種別
ポイント7業種中5業種で前年同月比減少
業種別に見ると、7業種中5業種が前年同月を下回った。なかでも、小売業(151件、前年同月比17.0%減)をはじめ、建設業(155件、同15.8%減)、卸売業(118件、同10.6%減)の3業種が前年同月比2ケタの減少率を記録した。一方、運輸・通信業(32件、同18.5%増)と製造業(103件、同1.0%増)の2業種は前年同月を上回った。
要因・背景
- 1. 建設業…東北の復興需要や、主に大都市圏での堅調な工事需要に支えられ、7月としては4年連続の前年同月比減少となった
- 2.小売業…消費税増税後の駆け込み需要の反動減が収束しつつあり、生活必需品の堅調な需要もあり、横ばいで推移した東北を除く全地域で前年同月を下回った
■主因別
ポイント「不況型倒産」の構成比84.4%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は646件(前年同月比8.1%減)となった。構成比は84.4%(前月82.7%、前年同月83.3%)と、前月を1.7ポイント、前年同月を1.1ポイントそれぞれ上回った。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、 業界不振を「不況型倒産」として集計
要因・背景
- 1. 「返済猶予後倒産」は37件(前年同月比2.6%減)判明
- 2. 「円安関連倒産」は24件(前年同月比9.1%増)判明し、19カ月連続の前年同月比増加
■規模別
ポイント負債5000万円未満の構成比56.6%
負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は433件(前年同月比8.8%減)で、構成比は56.6%と、前年同月を0.3ポイント上回った。一方、負債10億円以上の倒産は23件(同43.8%増)に上った。資本金別では、個人経営と資本金1000万円未満の合計が441件となり、構成比は57.6%を占めた。
要因・背景
- 1. 負債5000万円未満の倒産では、サービス業(115件、前年同月比13.3%増)が最多
- 2. 負債10億円以上の倒産(23件)、前年同月比43.8%の大幅増加
■地域別
ポイント9地域中6地域で前年同月比減少
地域別に見ると、9地域中6地域で前年同月を下回った。なかでも、北陸(16件、前年同月比42.9%減)、四国(12件、同33.3%減)は前年同月比3割以上の大幅減少となった。一方、九州(57件、同42.5%増)や北海道(31件、同40.9%増)は前年同月を大幅に上回った。
要因・背景
- 1. 北陸は新幹線開通の波及効果が続き、運輸・通信業や小売業が大きく減少
- 2. 九州は東九州自動車道の大分宮崎区間が全線開通し、周辺地域の公共工事が大幅に減少した影響もあり、建設業(18件、前年同月比157.1%増)が大幅増加
■上場企業倒産
上場企業の倒産は発生しなかった。
2015年の上場企業倒産は、スカイマーク(株)(1月、負債710億8800万円)、江守グループホールディングス(株)(4月、同711億円)の2件にとどまっている。
■主な倒産企業
負債トップは、(株)goodgo99(東京都、破産)の85億円。以下、(株)ジョー・コーポレーション(愛媛県、破産)の72億7500万円、(株)榎並工務店(大阪府、民事再生法)の49億4400万円、つくば管財(株)(茨城県、特別清算)の44億円がこれに続く。
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは45.4、国内景気は生産・消費活動への好材料が増えている
2015年7月の景気DIは前月比0.7ポイント増の45.4となり4カ月ぶりに改善した。
7月は、原油価格が1バレル=40ドル台(WTI)に下落したことで、ガソリンや軽油価格が低下し、中小運輸業の景況感を上向かせる要因となった。また、給与水準の上昇に加えて大手企業の夏季賞与妥結額が過去3 番目の高水準となるなど所得環境が改善したうえ、継続する円安水準を追い風に中国などからの訪日旅行客によるインバウンド消費が拡大したことで、個人消費関連が好調だった。堅調な設備投資や下げ止まり傾向のみられた公共工事もあり建設関連需要が高まったほか、普通乗用車の生産が上昇に転じたことで機械製造などが堅調に推移した。国内景気は、賃金上昇やインバウンド消費の拡大など生産・消費活動への好材料が増えている。
国内景気は回復力に勢いが感じられないものの、なだらかな上向き傾向が期待される
有効求人倍率の改善や失業率の低下など労働需給は引き締まった状態にあり、雇用者所得は上昇していくとみられる。さらに、建設や情報サービス、旅館・ホテルなどで人手不足が高水準となっており雇用状況の改善は続くと予測される。また、住宅着工戸数の持ち直しや大型のインフラ投資も高水準で推移するとみられるほか、自動車生産の持ち直しを通じた機械需要の回復や、米国経済の堅調な成長はプラス材料といえよう。今後の国内景気は、回復力に勢いは感じられないものの、なだらかな上向き傾向が期待される。
ただし、食品価格の上昇など個人消費が抑制されるリスクのほか、中国の成長鈍化で輸出が下押しされる可能性もある。これらが顕在化した場合、生産調整の長期化や企業の投資意欲の低下など景気が下振れする懸念は残る。
今後の見通し
■倒産件数は建設業や小売業の減少で低位推移、地域別動向やリスク要因は継続して注視
7月の倒産件数は765件と、4カ月連続で前年同月を下回り、依然として低位での推移となった。その要因として、倒産件数全体のそれぞれ約2割を占める建設業(155件、前年同月比15.8%減)、小売業(151件、同17.0%減)が前年同月比で2ケタ台の減少率となっている点がある。
東日本建設業保証の発表によると2015年6月の保証実績請負金額(全国)は前年同月比1.8%減と、公共工事は微減となり、これまでほどの勢いはなくなっている。一方で国土交通省が公表した2015年6月の住宅着工戸数は前年同月比16.3%増で4カ月連続増加、うち分譲住宅は同31.3%増、分譲マンションは同82.8%増と大きく伸びている。このように民需が公共工事を補う形となり建設業の倒産抑止効果につながっている。
また、小売業界では、日本百貨店協会発表の2015年6月の全国百貨店売上高は前年同月比0.4%増(店舗数調整後)と3カ月連続でプラスとなったほか、スーパーマーケット3団体による「スーパーマーケット販売統計調査」においても、6月の全店売上高(速報版)は前年同月比1.1%増(既存店ベース)と3カ月連続で増加しており、生活必需品などの動きも堅調だ。こうした個人消費の緩やかな回復傾向や、有効求人倍率の改善や賃金上昇など雇用・所得環境のプラス材料に加え、地域住民生活等緊急支援のための交付金(地域消費喚起・生活支援型、約2500億円)を活用した各自治体によるプレミアム付商品券等の発行や、インバウンドによる“爆買い”消費も追い風となり、小売業においても倒産件数の押し下げは続くだろう。
とはいえ、地域別に目を転じると一概に回復基調にあるとはいえない。7月は北海道(31件、前年同月比40.9%増)および九州(57件、同42.5%増)で、前年同月比の増加率が40%を超えた。公共工事への依存度が高い地方では、その動向を懸念する声は強いほか、賃上げ効果が大都市圏ほど大きくないため、個人の消費支出に慎重な姿勢もみられる。
景気が緩やかな回復傾向を示すなかで、倒産は当面低位で推移すると見込まれるが、地域別の景況感に加え、人手不足や原材料・資材価格の高騰、為替動向など、各種リスク要因は注視していく必要がある。
■金融機関に求められる適切な企業の事業性評価、支援スタンスに注目
金融庁が7月に公表した「金融モニタリングレポート」では、企業倒産が減少する中で金融機関の信用コストは2006年3月期以降最低レベルまで低下していると指摘する。
倒産が低位推移を続けている背景には、2013年3月末に中小企業金融円滑化法が終了した後も金融機関が返済猶予、リスケジュール等の支援を継続している点があり、貸付条件変更等の申込に対する実行率は2014年度下半期では96.9%と依然として9割を超えている。ただし、支援対象企業のなかには、経営改善計画に基づき再建に取り組みつつも、長期にわたる債務超過や借り入れ負担で財務体質が脆弱な企業も多い。景気回復途上で業況が拡大したとしても、新規の資金調達が厳しく、倒産を余儀なくされるケースは今なお散発している。
長期にわたり低金利が続くなかで、金融機関の貸出利ざやは減少傾向にある。特に人口減少が深刻化している地方において、今後とも地域経済を支える存在としてその役割を果たし続けるには、企業の事業内容や成長性などを適切に評価し、中長期的に支援・育成することで収益基盤を強化することが求められる。大きな政策転換が無い限りは倒産の急増はないが、債務超過などで先行き不透明な企業に対しても支援を継続するのか、または清算・廃業を促すのか、金融機関の今後のスタンス次第で緩やかに倒産が増加に転じる可能性は残されている。

