倒産件数は627件、2カ月ぶりの前年同月比減少
負債総額は757億3800万円、2000年以降最小
倒産件数 | 627件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲9.9% |
前年同月 | 696件 |
前月比 | ▲11.2% |
前月 | 706件 |
負債総額 | 757億3800万円 |
|---|---|
前年同月比 | ▲51.6% |
前年同月 | 1565億7200万円 |
前月比 | ▲38.9% |
前月 | 1238億6600万円 |
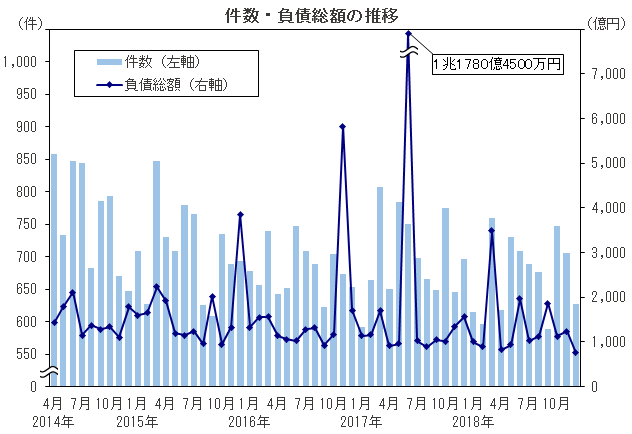
主要ポイント
- ■倒産件数は627件で、前年同月比9.9%の減少となり、2カ月ぶりに前年同月を下回った。負債総額は757億3800万円、前年同月比51.6%の減少と、2カ月連続で前年同月を下回り、2000年以降最小となった
- ■業種別に見ると、7業種中4業種で前年同月を下回った。このうち、建設業(100件、前年同月比17.4%減)は6カ月連続、卸売業(93件、同19.8%減)は3カ月連続の前年同月比減少。また、減少した4業種すべてで前年同月比2ケタの減少となった。一方、サービス業(149件、同4.9%増)は3カ月連続、不動産業(25件、同19.0%増)は2カ月連続の前年同月比増加となった
- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は502件(前年同月比11.3%減)となり、2カ月ぶりに前年同月を下回った。構成比は80.1%(同1.2ポイント減)を占めた
- ■負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は399件(前年同月比4.8%減)となった。構成比は63.6%を占め、小規模倒産が過半を占める傾向が続いた。資本金規模別では資本金1000万円未満(個人経営含む)の倒産が421件となり、構成比67.1%を占めた
- ■地域別に見ると、9地域中7地域で前年同月比減少となった。このうち、東北(17件、前年同月比58.5%減)は5カ月ぶり、北陸(14件、同12.5%減)、四国(14件、同22.2%減)は6カ月ぶりの前年同月比減少となった。一方、北海道(18件、同20.0%増)、中国(30件、同7.1%増)は前年同月を上回った
- ■負債トップは、イーター電機工業(株)(東京都、破産)の54億3600万円
調査結果
■件数・負債総額
ポイント倒産件数は627件、負債総額は2000年以降最小
倒産件数は627件で、前年同月比9.9%の減少となり、2カ月ぶりに前年同月を下回った。負債総額は757億3800万円、前年同月比51.6%の減少と、2カ月連続で前年同月を下回り、2000年以降最小となった。
要因・背景
件数…業種別では7業種中4業種で、地域別では東北や北陸など7地域で前年同月比減少
負債総額…負債100億円以上の倒産は発生せず、大型倒産は低水準が続く
■業種別
ポイント7業種中4業種で前年同月比減少
業種別に見ると、7業種中4業種で前年同月を下回った。このうち、建設業(100件、前年同月比17.4%減)は6カ月連続、卸売業(93件、同19.8%減)は3カ月連続の前年同月比減少。また、減少した4業種すべてで前年同月比2ケタの減少となった。一方、サービス業(149件、同4.9%増)は3カ月連続、不動産業(25件、同19.0%増)は2カ月連続の前年同月比増加。
要因・背景
- 1. 建設業は、堅調な建設需要を背景に、職別工事(40件、前年同月比13.0%減)、総合工事(38件、同19.1%減)、設備工事(22件、同21.4%減)のすべてで前年同月を下回った
- 2. サービス業は、パチンコホールやゲームセンターなどの娯楽業(13件、前年同月2件)と、整体・マッサージ等の施術所などの医療業(14件、同5件)が全体を押し上げた
■主因別
ポイント「不況型倒産」の構成比80.1%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は502件(前年同月比11.3%減)となり、2カ月ぶりに前年同月を下回った。構成比は80.1%(同1.2ポイント減)を占めた。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
要因・背景
- 1. 不況型倒産を業種別に見ると、サービス業(114件)が構成比22.7%を占め最多
- 2.「人手不足倒産」は20件(前年同月比25.0%増)、集計を開始した2013年1月以降で最多
- 3.「後継者難倒産」は36件(前年同月比20.0%増)、2カ月連続の前年同月比増加
- 4.「返済猶予後倒産」は46件(前年同月比2.2%増)、2カ月ぶりの前年同月比増加
■規模別
ポイント負債5000万円未満の構成比63.6%
負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産は399件(前年同月比4.8%減)となった。構成比は63.6%を占め、小規模倒産が過半を占める傾向が続いた。資本金規模別では資本金1000万円未満(個人経営含む)の倒産が421件となり、構成比67.1%を占めた。
要因・背景
- 1. 負債5000万円未満の倒産では、製造業(36件、前年同月比16.3%減)、小売業(98件、同15.5%減)の2業種が前年同月比2ケタの減少
- 2. 負債100億円以上の倒産は発生しなかった
■地域別
ポイント9地域中7地域で前年同月比減少
地域別に見ると、9地域中7地域で前年同月比減少となった。このうち、東北(17件、前年同月比58.5%減)は5カ月ぶり、北陸(14件、同12.5%減)、四国(14件、同22.2%減)は6カ月ぶりの前年同月比減少となった。一方、北海道(18件、同20.0%増)、中国(30件、同7.1%増)は前年同月を上回った。
要因・背景
- 1. 東北は、秋田県や福島県で卸売業、小売業などが前年同月を下回り、件数を押し下げた
- 2. 中国は、製造業(3件、前年同月1件)、小売業(11件、同8件)などで前年同月比増加
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは49.4、国内景気は2カ月ぶりに悪化
2018年12月の景気DIは前月比0.1ポイント減の49.4となり、2カ月ぶりに悪化した。 12月の国内景気は、幅広い業種で年末需要が発生したことから雇用過不足DI(非正社員)が過去最高を更新するなど人手不足に拍車がかかり、一部で受注機会の損失や進捗遅れにつながった。中国向け輸出の減速などを背景に製造業が悪化したほか、月末にかけ株価や為替相場など金融市場は不安定な動きとなった。他方、災害復旧・復興工事や住宅着工などの建設需要が堅調に推移し、燃料価格の低下や冬季賞与増加はプラス材料となった。
国内景気は年末需要がみられたものの、一方で人手不足に拍車をかけたほか、輸出減速などにともない製造業が悪化するなど、弱含み傾向が続いた。
消費税率引き上げの影響や、日米通商交渉の行方が懸念され、不透明感が一層強まる
今後、設備投資は省力化やシステム投資を中心に底堅く推移し、個人消費は良好な雇用・所得環境を受け、緩やかながら回復が続くであろう。2019年10月の消費税率引き上げを見据えた駆け込み需要が表れる一方、その後の反動減が懸念され、落ち込みの軽減に経済対策が一定の効果を果たすと期待される。海外動向は、中国などを中心に世界景気の減速を受け、輸出の増加基調が鈍化すると予想される。また日米物品貿易協定(TAG)の行方や、米金利政策・英EU離脱などを受けた金融市場の動向を注視していく必要がある。
今後は、消費税率引き上げにともなう需要増と反動減が予想されるほか、中国など外需の減速や日米通商交渉の行方が懸念され、不透明感が一層強まっている。
今後の見通し
■倒産件数は2年ぶりに減少、多数の消費者を巻き込んだ倒産相次ぐ
2018年の倒産件数は、8年ぶりの前年比増加となった前年から一転し、2年ぶりの減少となった。業況の改善や金融機関による資金繰り支援などを背景に建設、製造、卸の3業種が過去最少を記録した。負債5000万円未満の小規模倒産の割合が10年連続で上昇し、61.7%と最高を更新したことなどから、負債総額(1兆6255億5200万円)も過去最小となった。
2018年最大の負債は、磁気健康器具販売のネットワークビジネス大手だったジャパンライフ(3月、負債2405億円)となった。オーナー制度で広く資金を集め、被害対策弁護団も結成されたケフィア事業振興会(9月、同1001億9400万円)がこれに次ぐ大型倒産となったほか、シェアハウス「かぼちゃの馬車」を展開していたスマートデイズ(4月、同60億3500万円)、振り袖販売・レンタルでトラブルとなったはれのひ(1月、同6億3500万円)など、多くの個人投資家や消費者を巻き込んだことで注目を集めた倒産が相次いだ。
■建設業は10年連続減、今後は採算悪化で反転増も
2018年の建設業の倒産(1414件、前年比10.0%減)は過去最少となった。災害復興や国土強靭化に基づくインフラ整備需要のほか、都市部での大規模再開発の増加などを受け、直近ピークの2008年(3446件)以降、10年連続のマイナスで約4割にまで減少した。東京都と大阪府の減少が全体を大きく押し下げ、関東、近畿など計5地域で過去最少となった一方、震災復旧・復興工事が最盛期を過ぎた東北(81件、前年比26.6%増)などでは増加と、地域差もみられた。
政府は国土強靭化として事業規模7兆円程度の3カ年のインフラ対策を発表するなど、建設業は今後も公共事業を中心に底堅い受注動向が見込まれるものの、労務費や建材費の上昇による採算悪化を要因とした小規模企業の倒産増加も懸念される。
■後継者難倒産は前年比2ケタ増
後継者不在のため事業継続の見通しが立たなくなったことから倒産した「後継者難倒産」は、401件と前年比17.6%の増加で、調査開始以降の最多件数(2013 年、411 件)に迫った。経営ノウハウや取引先との関係、人脈などを代表個人に大きく依存した小規模企業では、代表の突然の体調不良や死亡などで事業継続が困難となり、倒産に追い込まれるケースが目立つ。また、後継者不在のまま債務超過状態で事業を継続し、円滑な廃業を選択できなくなった企業による倒産も散見された。代表の高齢化が進むなか、今後も後継者難倒産の動向が注目される。
■倒産件数は低水準が続く見込みも、山積するリスク要因への注視要する
2018年4月からスタートした信用補完制度の見直しにより、不況業種を対象としたセーフティネット保証5号の保証割合は100%から80%に引き下げられた。中小企業の資金繰りへの影響が注目されたものの、現時点で金融機関による融資先選別など、大きな変化はみられない。今後も同様の資金繰り環境が続くとすれば、引き続き倒産件数は低水準での推移が想定される。
10月に予定される消費税率の引き上げは、引き上げ前後の駆け込み需要と反動減が前回(2014年4月)よりも抑えられる見通しであり、倒産への影響は限定的だろう。他方、緩やかな景気回復が続く国内では、生産年齢人口の減少と相まって幅広い業種で人手不足感が高まっている。2018年の「人手不足倒産」(153件)は3年連続の増加で推移しており、今後さらなる増加も懸念される。また、世界経済全体に、米中貿易摩擦を背景とした不透明感が強まるなか、円高株安による企業業績不安は2019年最大の懸念材料であり、各種リスク要因には注視を要する。

