企業倒産、大幅減少トレンドに“底打ち”の兆し
今後は過剰債務企業の軟着陸が焦点に
倒産件数は482件、8カ月連続の前年同月比減少
負債総額は679億7000万円、1月として32年ぶりの低水準
倒産件数 | 482件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲4.7% |
前年同月 | 506件 |
負債総額 | 679億7000万円 |
|---|---|
前年同月比 | ▲25.5% |
前年同月 | 912億5800万円 |
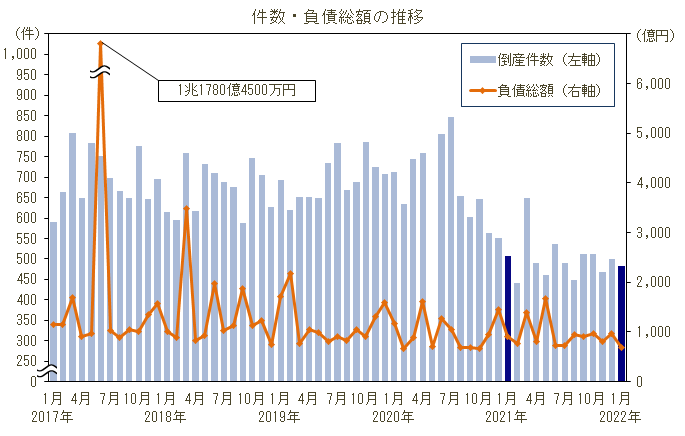
概況
倒産件数は482件、8カ月連続の減少も底打ちの兆し
倒産件数は482件と、前年同月(506件)から24件減少、前年同月比で4.7%減となった。8カ月連続の前年同月比減少も、減少率は2021年7月(42.1%減)をピークに低下傾向にあり、2ケタの大幅減が続いた倒産抑制に底打ちの兆しがみられる。
負債総額は679億7000万円と、前年同月(912億5800万円)から232億8800万円減少し、前年同月比で25.5%減。1月として1990年以来32年ぶりの低水準となった。
主要ポイント
- ■業種別にみると、7業種中4業種で前年同月比増加。建設業(前年同月90件→100件、11.1%増)は、資材価格や労務費の増加などにより、2ケタ増。一方、小売業(前年同月121件→90件、25.6%減)では、飲食店(同48件→33件)が過去最長となる8カ月連続の減少
- ■主因別にみると、「不況型倒産」の合計は388件(前年同月391件、0.8%減)と、8カ月連続で前年同月を下回った。構成比は80.5%(対前年同月3.2ポイント増)を占める
- ■負債規模別にみると、負債5000万円未満の倒産において、建設業(63件)が構成比21.4%(対前年同月4.9ポイント増)と、5年5カ月ぶりに20%超となった
- ■地域別にみると、9地域中6地域で前年同月比減少。近畿(前年同月141件→123件、12.8%減)は、特に飲食店(同19件→12件、36.8%減)で大幅減。一方、関東(前年同月180件→190件、5.6%増)では、東京都(同77件→89件)が8カ月ぶりに増加した
- ■人手不足倒産は10件(前年同月8件、25.0%増)発生、2カ月ぶりの前年同月比増加
- ■後継者難倒産は29件(前年同月31件、6.5%減)発生、4カ月ぶりの前年同月比減少
- ■返済猶予後倒産は35件(前年同月29件、20.7%増)発生、4カ月ぶりの前年同月比増加
■業種別
7業種中4業種で前年同月比増加、飲食店が過去最長となる8カ月連続の減少
業種別にみると、7業種中4業種で前年同月を上回った。建設業(前年同月90件→100件、11.1%増)は、資材価格や労務費の増加などにより、2ケタの増加となった。製造業(同42件→46件、9.5%増)では、建築用金属製品製造(同0件→2件)やコンクリート製品製造(同0件→2件)などの建築資材関連の倒産が発生したこともあり、8カ月ぶりに増加。
一方、小売業(前年同月121件→90件、25.6%減)では、飲食店(同48件→33件)が過去最長となる8カ月連続の減少。また、サービス業(同123件→120件、2.4%減)は、前年同月から微減にとどまったものの、診療所など医療業(同9件→15件)が前年同月比2ケタの大幅な増加となった。
■主因別
「不況型倒産」は388件、構成比は80.5%
主因別にみると、「不況型倒産」の合計は388件(前年同月391件、0.8%減)と、8カ月連続で前年同月を下回った。構成比は80.5%(対前年同月3.2ポイント増)を占めた。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産」として集計
■規模別
負債5000万円未満の構成比61.0%、建設業で5年5カ月ぶりの高水準
負債規模別にみると、負債5000万円未満の倒産は294件(前年同月321件、8.4%減)、構成比は61.0%を占めた。このうち、サービス業(79件)が構成比26.9%(対前年同月0.5ポイント減)を占め最多。建設業(63件)では、比較的小規模の倒産が多くみられ、構成比は21.4%(同4.9ポイント増)と、5年5カ月ぶりに20%超となった。
資本金規模別では、資本金1000万円未満(個人事業主含む)の倒産が321件(前年同月358件、10.3%減)、構成比は66.6%を占めた。
■地域別
9地域中6地域で前年同月比減少も、東京都は8カ月ぶりの増加
地域別にみると、9地域中6地域で前年同月から減少した。近畿(前年同月141件→123件、12.8%減)は、特に飲食店(同19件→12件、36.8%減)で大幅な減少となった。また、中部(同74件→50件、32.4%減)では、長野県以外の5県で2ケタの減少率を記録した。
一方、関東(前年同月180件→190件、5.6%増)など3地域では、前年同月から増加した。関東では、東京都(同77件→89件)が8カ月ぶりに増加。東北(同17件→33件、94.1%増)は、建設業(同1件→11件)が大幅に増加し、全体の件数を押し上げた。
■態様別
「破産」は441件、構成比91.5%
態様別にみると、破産は441件(構成比91.5%)。特別清算は25件(同5.2%)となった。民事再生法は16件で、うち10件を個人事業主が占めた。
■特殊要因倒産
人手不足倒産
10件(前年同月8件、25.0%増)発生、2カ月ぶりの前年同月比増加
後継者難倒産
29件(前年同月31件、6.5%減)発生、4カ月ぶりの前年同月比減少
返済猶予後倒産
35件(前年同月29件、20.7%増)発生、4カ月ぶりの前年同月比増加
※特殊要因倒産では、主因・従因を問わず、特徴的な要因による倒産を集計
■景気動向指数(景気DI)
オミクロン株の影響で国内景気は5カ月ぶりに悪化
2022年1月の景気DIは前月比2.7ポイント減の41.2となり、5カ月ぶりに悪化した。
1月の国内景気は、新型コロナウイルスの新規感染者が一日当たり8万人台へ急増したことに加えて、大雪の影響も下押し要因となった。全国34都道府県がまん延防止等重点措置の対象地域となったことで、外出の自粛や営業時間の短縮など、企業活動が再び抑制。さらに、自動車工場の減産や稼働停止に加えて、原材料価格や原油など燃料価格の上昇は、企業の収益環境を下押しする要因となった。他方、一部の企業ではEコマースや宅配関連がプラス材料のほか、自宅内消費も引き続き好調だった。
国内景気は、感染者数の急増で企業活動が再び抑制されるなど、大幅に落ち込んだ。
今後は一時的な落ち込み後に緩やかな回復の見込み
今後の国内景気は、オミクロン株など新型コロナウイルスの感染拡大による経済活動の抑制と緩和時期に大きく左右される。また、原油など原材料価格の高騰・高止まりによるガソリンや軽油・重油など燃料価格の上昇、地政学的な不確定要素は下振れリスクである。さらに、賃上げの動向のほか、人手不足の高まりや人材採用など、労働力確保に向けた動きも注視を要する。他方、リベンジ消費や旺盛な自宅内消費の継続、5G関連の環境整備、半導体需要の増加などはプラス材料となろう。また、新規感染者数の減少とともに対面型サービス需要の拡大や自動車などの挽回生産も見込まれる。
今後は、一時的な落ち込み後に緩やかな回復が見込まれるものの、下振れリスクの動向に注視する必要がある。
今後の見通し
■企業倒産、大幅減少トレンドに“底打ち”の兆し 1月の減少率、コロナ禍以降で2番目の低さ
2022年1月の倒産件数は482件となった。1月としては2000年1月(354件)以来となる500件割れとなり、前年に続いて低水準でのスタートとなった。引き続き、コロナ関連の経営支援策が行きわたり、多くの中小零細企業で資金繰りひっ迫の事態が回避された状態が続いており、倒産の発生は大きく抑制された状態が続いている。ただし、前年1月からの減少率は4.7%となり、2カ月連続で減少率が1ケタで推移したほか、減少トレンドに転じた2020年8月以降、2番目に低く、21年7月の42.1%減をピークに縮小が続いている。長く続いた企業倒産の大幅減トレンドはここに来て底打ち感の兆しもみられており、年度末となる3月にかけては急増局面こそ無いとみられるものの、緩やかな反転増となる可能性も見えている。
負債総額は679億7000万円で、前年同月から25.5%の大幅減少となった。まつえ環境の森(産業廃棄物処理、民事再生、負債約45億円)など大型倒産は複数発生したものの、負債が30億円を超える倒産は依然として少ない。総じて、負債額の小さな小規模・零細事業者の倒産が圧倒的多数を占める状況に変化はない。
■生活必需品、エネルギー…相次ぐ値上げも「価格転嫁できない」6割、小売業へのしわ寄せ警戒
トマトケチャップ、菓子パン、コーヒー、ソーセージ、ウイスキー…食品から文房具まで、幅広い品目での値上げラッシュが続いている。エネルギー価格の上昇も止まらず、3月から電力大手や都市ガス大手が値上げの予定。レギュラーガソリンの全国平均価格(1リットルあたり)も1月には13年ぶりに170円を超えた。コロナ禍から経済が回復する世界各国の需要増に供給量が追い付かず、世界的に価格が高騰している。国内ではこうした価格高騰に加え、急速に進行する円安の影響で輸入コストがさらに上乗せされる。結果、人件費の抑制や効率化といった企業努力により吸収可能な範囲を既に超えたことが、相次ぐ価格改定に繋がった要因となっている。
ただし、こうした原材料高を価格に反映できるケースは一部の大企業に限られ、多くの中小企業では値上げができていない実態がある。帝国データバンクの調査では、企業の約6割で仕入価格が前年同月を上回るとした一方、そのうち半数超で販売価格への転嫁ができていなかった。ウッドショックをはじめ品薄状態だったケース、事業者間取引のケースでは「値上げやむなし」の雰囲気も浸透しているものの、値上げの割合が3割にとどまる飲食店や食品製造など消費者に直結する業界では、物価上昇が進むなかでも価格改定が難しい状況となっている。
過去の小売業の倒産事例では、仕入価格上昇時に消費マインドの低下を警戒し、価格転嫁をしなかった結果、しわ寄せを受けた末に資金繰り難に陥り、経営が行き詰ったケースが少なくなかった。翻って現在をみると、足元ではこれら業種の倒産は総じて減少傾向にあり、急増に転じる兆候はみられない。ただし、黒田東彦・日本銀行総裁は、足元の物価上昇は一時的との見方から「現在の金融緩和を修正する必要は全くない。利上げの議論すらしない」との姿勢を堅持しており、国内の物価上昇が止まる気配は今のところなさそうだ。そのため、人手不足で人件費が上昇するなど現状でも利幅が薄く、価格競争を強いられる小売業にさらなるコストアップのしわ寄せが集中してしまう事態を当面は警戒しなければならない。
■過剰債務企業の軟着陸が焦点 新たに用意される私的整理スキーム、事業再生の実効性が課題
今後は、ゼロゼロ融資をはじめコロナ禍で増えた中小企業の「過剰債務問題」をいかに軟着陸させるかが焦点となる。帝国データバンクが保有する財務データを分析すると、2021年4-12月期までの有利子負債は月商対比でコロナ前から1カ月分増の5.6倍に膨張、今後さらに膨らむ可能性もある。こうしたなか、全国銀行協会は、金融機関による債務減免などを中心とした中小企業版「私的整理ガイドライン」の骨子を固め、4月から加盟行に対して運用を求める方針だ。
今回の特徴は、コロナ禍などの影響に配慮し、経営責任が大きく問われないインセンティブが用意される点となりそうだ。退任や債務保証など経営責任の追及を恐れ、事前の相談に消極的となりやすい中小零細企業の経営者が相談・決断できるように各種の要件が緩和される見通しだ。そのため早期の問題発見や事業再生につながり、相談が遅れたために事業再生が間に合わず法的整理を余儀なくされるケースを減らす効果が期待できよう。ただし、既に事業利益で利息を支払うことができない破たん懸念企業が30万社あると推計されるなか、債務減免や返済猶予とセットになるはずの「事業再建」がどれだけ実行・完了できるのか、という懸念は残る。
過去の私的整理スキームや債務減免でも、すべての企業が円満な出口戦略を描けてきたわけではない。金融円滑化法でリスケ対応した企業の経営改善計画も、策定できた企業は全体の3割程度にとどまった苦い歴史もある。今回用意された私的整理スキームも、抜本的な再建計画の策定とその“実効性”が担保できなければ、「“倒産の先送り“という轍を再び踏むのではないか」との懸念も根強い。倒産動向に与える影響を含めて、先行きが注視される。

