倒産件数は627件、19カ月連続の前年同月比減少
負債総額は1652億8300万円、2カ月ぶりの前年同月比増加
倒産件数 | 627件 |
|---|---|
前年同月比 | ▲18.0% |
前年同月 | 765件 |
前月比 | ▲11.4% |
前月 | 708件 |
負債総額 | 1652億8300万円 |
|---|---|
前年同月比 | +41.8% |
前年同月 | 1165億4300万円 |
前月比 | +3.2% |
前月 | 1601億円 |
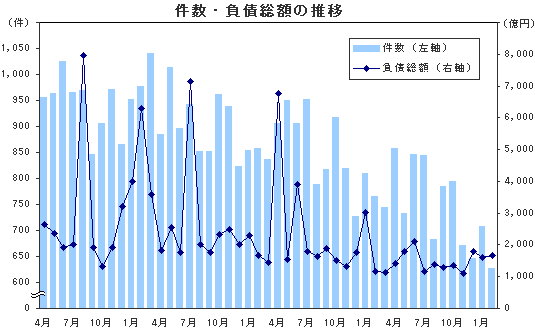
主要ポイント
- ■倒産件数は627件で、前年同月比18.0%の大幅減少となり、19カ月連続で前年同月を下回った。2ケタの大幅減少は5カ月連続となり、2005年5月(614件)以来の低水準となった
- ■負債総額は1652億8300万円で、前年同月から41.8%の大幅増加を記録し、2カ月ぶりの前年同月比増加となった
- ■業種別に見ると、7業種すべてが前年同月比2ケタの減少となった。なかでも建設業(118件、前年同月比20.3%減)は29カ月連続の前年同月比減少を記録したほか、卸売業(102件、同16.4%減)が15カ月連続の前年同月比減少となった
- ■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は533件(構成比85.0%)となった
- ■「円安関連倒産」は42件判明、食品やアパレル関連の業種の増加が目立つ
- ■負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は340件で、前年同月を16.7%下回ったものの、構成比は54.2%と28カ月連続で過半数を占めた。一方、負債10億円以上の倒産は31件と、8カ月ぶりに30件を上回った
- ■地域別に見ると、9地域中6地域で前年同月を下回り、6地域とも前年同月比2ケタの大幅減少となった。なかでも、中部(76件、前年同月比38.2%減)は30%以上、関東(213件、同20.2%減)は前年同月比20%以上の大幅減少となった
- ■上場企業倒産は発生せず、2014年度の上場企業倒産は1件と低水準にとどまっている
- ■負債トップは、蒲郡海洋開発(株)(愛知県、特別清算)の313億9100万円
調査結果
■件数・負債総額
ポイント件数は19カ月連続前年同月比減少、負債総額は2カ月ぶりの前年同月比増加
倒産件数は627件で、前年同月比18.0%の大幅減少となり、19カ月連続で前年同月を下回った。2ケタの大幅減少は5カ月連続となり、2005年5月(614件)以来の低水準となった。負債総額は1652億8300万円で、前年同月から41.8%の大幅増加を記録し、2カ月ぶりの前年同月比増加となった。
要因・背景
件数…公共工事が高水準で推移していることを受け、建設業(118件、前年同月比20.3%減)の減少が続いたほか、関東(213件、同20.2%減)の製造業、小売業で減少が目立つ
負債総額…負債10億円以上の倒産が31件と、8カ月ぶりに30件を上回る
■業種別
ポイント7業種すべてが前年同月比2ケタ減少
業種別に見ると、7業種すべてが前年同月比2ケタの減少となった。なかでも建設業(118件、前年同月比20.3%減)は29カ月連続の前年同月比減少を記録したほか、卸売業(102件、同16.4%減)が15カ月連続の前年同月比減少となった。また、サービス業(124件、同10.8%減)は2006年9月(108件)以来の低水準となった。
要因・背景
- 1. 建設業…公共工事に支えられ、土木工事(16件、前年同月比27.3%減)を中心に減少
- 2.製造業…大手メーカーの好業績もあり、機械器具(9件、前年同月比47.1%減)や電気機器(8件、同38.5%減)などの減少が目立つ
■主因別
ポイント「不況型倒産」の構成比85.0%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は533件(前年同月比17.4%減)となった。構成比は85.0%(前月83.8%、前年同月84.3%)と、前月を1.2ポイント、前年同月を0.7ポイントそれぞれ上回った。
※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、 業界不振を「不況型倒産」として集計
要因・背景
- 1. 「返済猶予後倒産」は31件(前年同月比20.5%減)判明
- 2. 「円安関連倒産」は42件判明、食品やアパレル関連の業種の増加が目立つ
■規模別
ポイント負債5000万円未満の構成比54.2%
負債額別に見ると、負債5000万円未満の倒産は340件で、前年同月を16.7%下回ったものの、構成比は54.2%と28カ月連続で過半数を占めた。一方、負債10億円以上の倒産は31件と、8カ月ぶりに30件を上回った。資本金別では、個人経営と資本金1000万円未満の合計が370件、構成比は59.0%を占めた。
要因・背景
- 1. 負債5000万円未満の倒産、業種別では小売業(100件、構成比29.4%)が最も多い
- 2. 大企業・中堅企業の業績回復や資金繰り改善を受け、大型倒産は低水準で推移
■地域別
ポイント9地域中6地域で前年同月比減少
地域別に見ると、9地域中6地域で前年同月を下回り、6地域とも前年同月比2ケタの大幅減少となった。なかでも、中部(76件、前年同月比38.2%減)は30%以上、関東(213件、同20.2%減)は前年同月比20%以上の大幅減少となった。一方、北海道(22件、同15.8%増)、四国(18件、同12.5%増)、九州(54件、同3.8%増)の3地域は前年同月を上回った。
要因・背景
- 1. 関東は、東京都の製造業、小売業を中心に減少し、過去10年で最少を記録
- 2. 中部は、静岡県の製造業、愛知県の小売業で減少目立ち、前年同月を38.2%大きく下回る
■上場企業倒産
上場企業倒産は発生しなかった。
2014年度の上場企業倒産は1件で、依然として低水準にとどまっている。
■主な倒産企業
負債トップは、「ラグーナ蒲郡」を運営していた蒲郡海洋開発(株)(愛知県、特別清算)の313億9100万円。(株)志正堂(東京都、特別清算)の100億円、東海開発(株)(東京都、民事再生法)の87億2400万円が続く。
■景気動向指数(景気DI)
景気DIは45.1、国内景気は全国的に底入れ
2015年2月の景気DIは前月比1.2ポイント増の45.1となり2カ月連続で改善した。2月の国内景気は、日経平均株価が15年ぶりの高値をつけるなど、原油安や賃金上昇への期待もあり景気が底入れしたとの見方が広がった。円安による自動車輸出の増加が関連業種へと波及したうえ、訪日旅行客の増加は小売や旅館・ホテルなどを上向かせた。原油価格下落は天然ガスの価格低下にもつながりはじめるなど、企業のコスト負担を一段と軽減させる要因となった。その結果、設備投資意欲が改善し資金需要も高まっているなか、工作機械など生産関連受注も活発化し、11カ月ぶりに全10地域が改善した。国内景気はエネルギー価格の低下や円安の好影響で消費税率引き上げ後の悪化傾向から脱し、底入れした。
今後は外部要因がけん引しつつ緩やかに改善する見込み
原油価格の下落によって企業や家計のエネルギー関連の負担が軽減されるほか、今後の設備投資や消費回復に向けた好材料として期待される。政府による経済対策とともに、地方創生や農業改革を踏まえた新しい成長戦略の実行が見込まれる。また、震災復興に加えて、高速道路や新幹線などインフラ整備の計画、東京五輪など建設需要は高水準で続くとみられる。さらに、2015年度に3.2兆円規模の賃上げが試算されていることも個人消費にとって好材料といえよう。ただし、人手不足は景気拡大を抑制する懸念材料となり、過剰分野から不足分野への労働力の移転がカギを握る。今後の国内景気は、外部要因がけん引しつつ緩やかに改善すると見込まれる。しかしながら、夏以降に新たな景気対策が打ち出されなければ横ばいで推移すると予想される。
今後の見通し
■消費税率引き上げ分の価格転嫁が進むも、エネルギーコスト上昇分は困難
消費税率の引き上げからまもなく1年が経過する。経済産業省が2月に行った「消費税の転嫁状況に関する月次モニタリング調査(書面)」によると、事業者間取引で85.1%、消費者向け取引では76.2%の事業者が「全て転嫁できている」と回答した。これは昨年4月に調査を行った時点(事業者間:79.0%、消費者向け:69.3%)からそれぞれ6ポイント程度改善しており、消費税の転嫁への理解は広まっていると言えよう。それでも「消費税を転嫁できないことによる収益性悪化」「消費税率引き上げに伴う駆け込みの反動減」など経営に影響が及んでいるケースもある。近い将来実施される見込みの再引き上げの際、この経験を生かした適切な対応が求められる。
他方、エネルギーコスト上昇分の価格転嫁は、容易ではない。2014年夏頃から続いている原油価格の下落について、底打ちの兆しありと見る向きがある。WTI原油先物価格は、1月に1バレル40ドル台半ばで推移していたが、2月に入ってからは1バレル50ドルを挟んだ推移が続いた。これを受け、レギュラーガソリン・軽油の店頭現金小売価格は、これまでの29週連続値下がりから反転し3週連続で値上がりしている(資源エネルギー庁、3月2日時点)。今までの値下がり分を打ち消すほど急上昇しているわけではないが、中小企業では、燃料費負担が軽くなったことで、円安に伴う輸入原材料価格高騰の影響が緩和される状況が続いていただけに、今後のコスト上昇による悪影響が懸念される。
また、電気料金値上がりの影響も見過ごせない。昨年6月に帝国データバンクが発表した「電気料金値上げに対する企業の意識調査」では、東日本大震災後の法人向け電気料金値上げに際し、6割超の企業が値上がり分の転嫁困難という状況にあった。その後、徐々に価格転嫁が進んでいるとみられるが、いまだ「電気料金値上げで収益性が悪化した」との声も聞かれるのが現実である。政府は3月3日、発送電分離を含む電気事業法の改正案を閣議決定した。これにより、将来的に電気料金を抑制する効果が期待されているとはいえ、当面、厳しい状況は変わらない。
■10年前は600件前後で倒産件数が底打ち、構造不況の解消がカギか
627件という倒産件数は、2005年5月(614件)以来の低水準。2005年は、小泉政権下で株価が上昇、TDB景気動向指数も40台前半から40台後半へ上昇した。企業倒産を見ると、過剰債務によるバブル型倒産から、本業不振による不況型倒産へ倒産の主流が推移するなか、セーフティネット保証、資金繰り円滑化借換保証など政府の支援策によって中小企業の倒産が抑制されている状態であった。当時、倒産は当面小康状態が続くと見られていたが、振り返れば、この2005年前半が倒産件数減少トレンドの底となり、その後増加に転じている。政府の中小企業支援策は確かに倒産件数を抑制した。しかし、それと同時に、不振企業が市場に居座り続けた結果、値下げ競争等の消耗戦を誘発。これにより構造不況の解消が妨げられ、後に、改正建築基準法や改正貸金業法の負の側面と相俟って、倒産増加要因の一つとなったのである。
それから10年。企業倒産件数は、中小企業金融円滑化法等の支援策により2008年度をピークに減少傾向をたどっている。2009年12月から2014年9月までに貸付条件の変更等が実行された中小企業者向け債権は約574万件(金融庁)。最大40万社が条件変更を受けていると推定される。出口戦略の重要性が叫ばれて久しいが、この数年間の倒産減少局面が不振企業に対する単なる延命措置の結果の表れであれば、10年前の繰り返しになる可能性は否定できない。確かに“アベノミクス”で株価は上がり、公共工事は増え、円安効果により大手輸出企業の収益性は大幅に回復した。しかし、コスト上昇による収益性低下、消費税率引き上げ等に起因する消費マインドの冷え込み、中国や欧州の景気下振れなど、中小企業が警戒を要するリスクが存在しているのも事実である。2014年度の倒産件数は、2005年度以来9年ぶりに9000件を下回る可能性が出てきた。注目は、2005年と現在に共通点が多くあること。例えば、地域として、業界として、そして個別企業として、構造的な問題は解消されていない。経営再建が進んでいない企業や、さらなる構造変化についていけない企業を中心として、再び消耗戦に突入することがあれば、それは2005年の再現とも言え、今後、企業倒産件数は徐々に増加傾向に遷移すると想定せざるを得ない。

